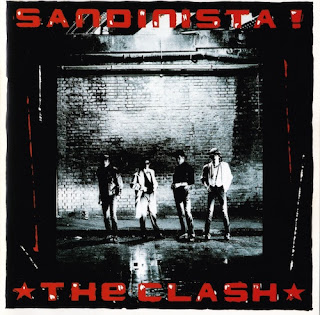私の放浪音楽史 Vol.41 THE CLASH『SANDINISTA!』
クラッシュの4枚目のアルバムは3枚組の大作となった。おそらくリリースされてすぐ聴いたと思うけど、全てを聴くのに約2時間25分、アナログ・レコード3枚をかけては裏返し、かけては裏返し、通して聴くのはそれなりの覚悟と忍耐(大げさだな…)が必要だった。当時の私のパンクロックあがりの耳に、このアルバムのヴァラエティに富んだ内容はやたらとっちらかって聴こえたものだ。パンク・ロック・スタイルの曲は「Somebody Got Murdered」、「Up In Heaven(Not Only Here)」、イコールズのカヴァー「Police On My Back」の3曲でいずれもミック・ジョーンズがヴォーカルをとっている。この3曲は当時も好きだった曲。それ以外はラップ、ロカビリー、レゲエ、ダブ、カリプソ、ソウル、ディスコ、ゴスペル…と多岐にわたるジャンルの楽曲が収録されている。
アルバム冒頭、シングルとしても発売された「The Magnificent Seven」はラップを取り入れた曲で、ノーマン・ワット・ロイのベースフレーズが気持ちよく(ポールは映画の仕事が入っていた)、歯切れのいいジョーのラップも魅力たっぷり。ここまでクラッシュが変貌を遂げたことに驚いたが、この新しいスタイルがまたカッコよかった。この曲がシュガーヒル・ギャングの「Rapper's Delight」(1979年)からの影響下にあると知ったのはずーっと後の事だ。
UKインディ賛歌でモータウン調の「Hitsville UK」、ディスコ・サウンドのトッパーが歌う「Ivan Meets G.I.Joe」、ジョーが101'ersでも取り上げていた古いR&Bでレゲエアレンジのカヴァー「Junco Partner」、ロカビリー「The Leader」、移民・戦争・核・高齢化など今日的な内容が歌われている「Something About England」は、ヴォーカルがミックからジョーに引き継がれていくメランコリックな曲で今回聴きなおしていいなと思った曲だ。ここまでアナログA面。
「Rebel Waltz」は反逆者たちに捧げる幻想的なワルツの調べ。モーズ・アリソンのカヴァー「Look Here」はトッパーのドラミングがクールで、ミッキー・ギャラガーの冴えわたるピアノ・プレイが最高なジャズ・ナンバー。「The Cracked Beat」はポール・シムノンがヴォーカルを取るレゲエ/ダブ曲。「Somebody Got Murdered」をはさんで、レゲエ「One More Time」と、 そのダブ・ヴァージョン「One More Dub」でB面が終わる。
アナログ2枚目の始まりは再びラップ調の「Lightning Strikes(Not Once But Twice)」で、A面冒頭の「The Magnificent Seven」と比べるとファンキーなグルーヴに欠けているのが残念だが好きな曲。ミックが歌う「Up In Heaven(Not Only Here)」に続いて、“Is the music calling for a river of blood ?”という印象的なフレーズが歌われる 「Corner Soul」はジョーの力強いヴォーカルが耳に残る。「Let's Go Crazy」はカーニヴァルの騒乱とパワーを歌ったカリプソ調の曲で、この曲を聴いたときもクラッシュは変わったなぁと私の耳は混乱したものだ。「If Music Could Talk」はリラックスしたムードの演奏に、左右のチャンネルからそれぞれ別々のジョーのヴォーカルが聴こえるというもの。イマジネーションの洪水のようなジョーのリリックも聴きものだ。 C面の終りはゴスペル風の「The Sound of The Sinners」で、“決して崩せない壁”を崩せるようなサウンドを求めていたジョーの告白、といった内容か。
アナログD面はギターがポリスカーのサイレンを模したサウンドの「Police On My Back」で始まる。ロカビリーで軽く流したような「Midnight Log」、「The Equaliser」は平等を訴えるダブ/レゲエ曲で、タイモン・ドッグのヴァイオリンがアクセントで効いている。「The Call Up」は軍の“召集に応じなるな”と呼びかける、シングルカットされた曲。アルバムタイトルの“サンディニスタ”が歌いこまれた「Washington Bullets」は、1979年のニカラグアの革命をテーマに16ビートにのせた曲。サンディニスタとはその革命運動の中心だったサンディニスタ民族解放戦線のことであり、ニカラグア革命の別名でもある。他国の政変にアメリカが(“ワシントンの銃弾”が)どう関与したのかをジョーは歌い、またロシアの、イギリスの銃弾についても言及する。「Broadway」はフリージャズとレゲエをミックスしたようなストレンジなサウンド。ジョーが最初呟くように歌っているが徐々に盛り上がりを見せる。この曲のエンディングでミッキーの弾くピアノにのせて子供達が歌う「The Guns of Brixton」を聴いてD面(アナログ2枚目)終了。
アナログ3枚目、E面の最初には、レコーディング中にニューヨークで再会したタイモン・ドッグの曲「Lose This Skin」を取り上げた。ヴァイオリンが鳴り響くサウンドはこのアルバムの中でも異色。ヴォーカルはタイモンがとっている。
「Charlie Don't Surf」は映画『地獄の黙示録』(1979年フランシス・フォード・コッポラ監督)に影響を受けて書かれた曲。映画の中でベトコン掃討作戦中に絶好の波が来る場所を見つけた米軍のキルゴア中佐はサーフィンを始めるが、 もちろん砲弾や銃弾が飛び交う戦闘中では思うように波に乗れない。彼は自分たちがサーフィンをするために戦闘機に指令を出し、ナパームをつかってベトコンを黙らせる。ここで彼が言う「朝のナパームの匂いは格別だ」は彼の特異なキャラクターを象徴している。アメリカ≒サーフィンをベトナム(の戦場)に持ち込み、サーフィンをすることがアメリカ人としてのアイデンティティである事を宣言するかのように「奴ら(チャーリー)はサーフィンをしない!」と言い放つ。個人的にはこの曲が『サンディニスタ!』を代表する1曲でもあると思う。オープニングのエフェクトがヘリのローターの回転音のように聴こえる。
「Mensforth Hill」はA-6「Something About England」を逆回転させた実験作。「Junkie Slip」は禁断症状を綴った作品でクラッシュ版“コールド・ターキー”か。実験的な作品が2曲続いたが、そんなサウンドをスパイス的に効かせてポップ・ロックに変換したような「Kingston Advice」をはさみ、E面の最後はやはり実験的な「The Street Parade」。
さて、ようやく最終F面に辿り着いた。「Version City」はファンキーな味付けの曲。バージョンシティの列車に乗り込み、 “アカペラ線を抜け、ギブソン街、フェンダー村、ブギー牧場へ向かって”クラッシュの旅は続く。マイキー・ドレッド作の「Living In Fame」はダブ・サウンドでヴォーカルはもちろんマイキー。トラックはC-5「If Music Could Talk」に似てる。「Silicone On Sapphire」はD-5「Washington Bullets」のダブ・ミックス。「Version Pardner」もA-3「Junco Partner」のダブ・ミックス。ミッキー・ギャラガーの子供達が歌う可愛らしいサウンドにつくりかえられた「Career Opportunities」が何ともシニカル。アルバムの最終曲「Shepherds Delight」は旅の終りとでも言いたげな、のんびりしたトラックが2分半ほど続き、発射音のような列車の通過音のような効果音で幕を閉じる。全36曲。
当時のロック・クリティックからは長すぎる、未消化・未完成の曲が多い、などと酷評され、ファンの間でも評判は悪かった。私のまわりでも同じで、これまでのパンクロックのアルバムのようなコンパクトにまとまったものとは違い過ぎた。それでもいくつかの曲は評判が良かったし、ジャケットもカッコ良かった(このジャケ写のバッジ持ってたんだけどな…)。CDでは2枚組となってリリースされたが、確かにCDとなってこのアルバムは聴き易くなった。収録曲の多さもまるでCD時代を先取りしているかのようだ。今では多くの評論家/アーティストがこのアルバムに収められた多種多様なサウンドを絶賛している。