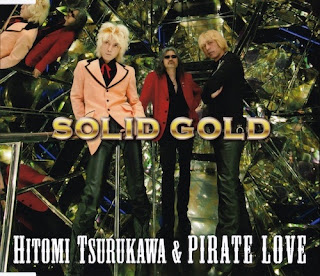追悼・大滝詠一「さらばシベリア鉄道」

2013年末、日本のロック・ポップスの巨星が逝ってしまった。あまりに突然に…。 大滝詠一。1981年のアルバム『A Long Vacation』。リリース当時、パンク・ニューウェイヴに傾倒していた自分にとっても、その歌声は届いた。だけど、2001年の20周年記念盤かな、その偉大さをあらためて認識したのは。「雨のウェンズディ」は自分のテーマ・ソングと思うようになったり…。リリース当時「さらばシベリア鉄道」は太田裕美のヴァージョンも良く流れていたっけ。 伝えておくれよ 十二月の旅人よ いついついつまでも待っていると 長らく途絶えていた大滝詠一の新作発表だが、“次”は永遠になくなってしまった。