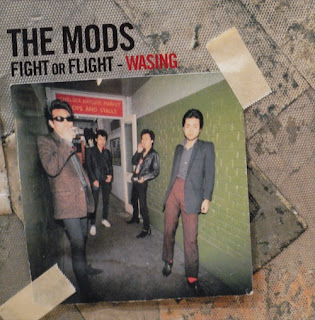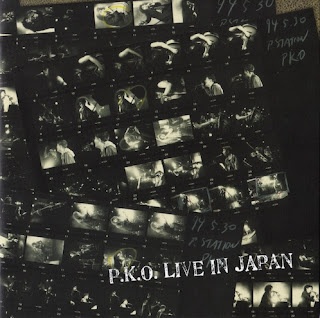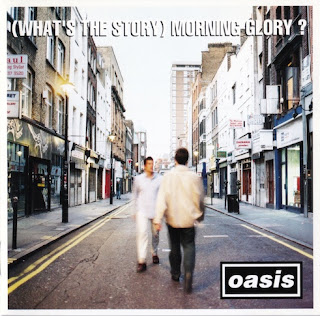CHATMONCHY「惚たる蛍」

2005年11月発表の『Chatmonchy Has Come』より。 今や大ブレイクしたチャットモンチーのメジャー・デビュー盤。 何が気になったかというと、ジャケットが1980年代初め頃によく聴いていたアメリカのバンド、The Feeliesの『Crazy Rhythms』のジャケットによく似てる。The Feeliesの1stアルバムだった『Crazy Rhythms』はギターがシャカシャカ、ドラムはタムタムを多用したドコドコなサウンドだったが、 ユルいだけではない楽曲のシャープさを持っていた。 チャットモンチーは飾り気の無い言葉(といっても表面的なものに終わっていない)をグランジ後のサウンドにのせて聴かせる。ボーカル&ギターの橋本絵莉子は高校時代から遊ぶ暇も惜しんで練習していたというだけあって、メロディ、曲の構成や演奏力は確かでオリジナルなものを感じさせる。収録された6曲は緩急つけた選曲でどれも楽しめるが、 “真っ暗の中で光る蛍は まるで私の体の中の悪い部分のように” という一節がひっかかるスローなこの曲を選んだ。 Drum Technicianとしてクレジットされているのは三原重夫。