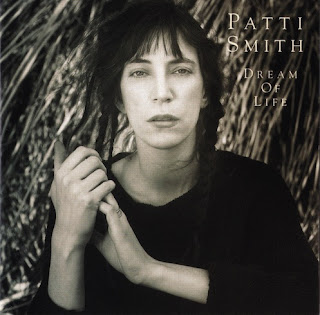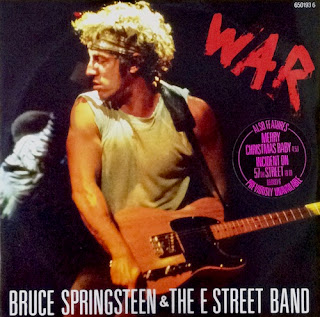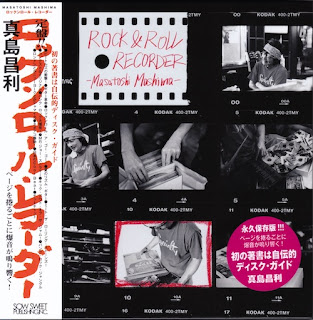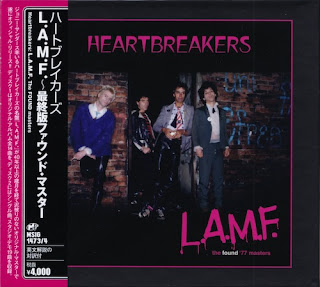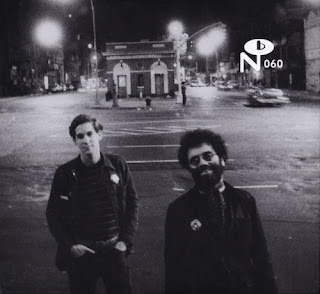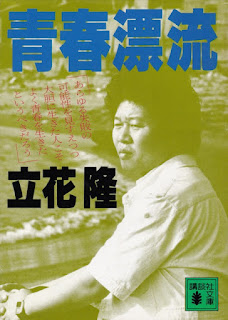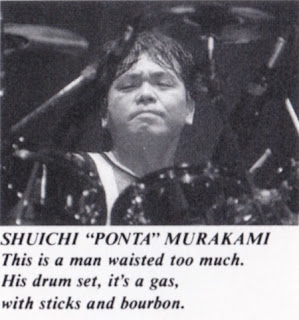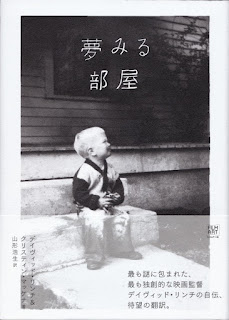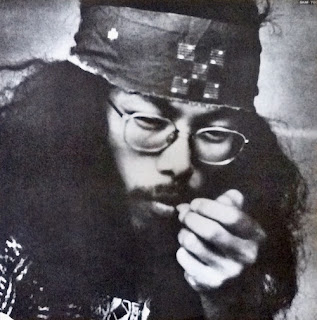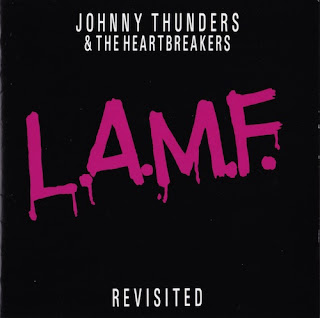1984年10月21日、COLUMBIA VIDEO/日本コロムビアよりリリース。 1984年7月15日に東京港区のラフォーレミュージアム赤坂でおこなわれたライヴをヴィデオ・シューティングした作品でルースターズにとっては初のヴィデオ作品だった。監督は『狂い咲きサンダーロード』、『爆裂都市・バーストシティ』の石井聰亙、プロデューサー緒方明、撮影監督・笠松則通と石井映画でおなじみの面々。白くまるで白骨のような木々が並ぶ風景や建物を飲み込んだ溶岩が固まっている風景の映像は、おそらく1983年の三宅島噴火後に撮影したものと思われる。 ラフォーレミュージアム赤坂は1983年7月23日〜8月7日にブライアン・イーノの「ビデオアートと環境音楽の世界」を開催してオープンした多目的スペースで、ローリー・アンダーソンの日本公演が1984年6月15日〜17日におこなわれている他、NYから帰国した佐野元春がツアー直前の1984年9月にメディア向けコンヴェンションをおこなった場所でもある。 当時このソフトはVHS、ベータ共テープが12,800円、レーザー・ディスクが7,800円という高額商品。この作品だけじゃなく60分以上の映画や音楽ソフトの販売価格はテープだと1作品1万円台、レーザーディスクが少し安いという設定。なので個人的には映像作品は買うものではなくレンタルショップで借りて観るものだった。この『パラノイアック・ライヴ』はレンタルがあったのかわからないが、何年か後に友人のKBちゃんに観せてもらった。それに『パラノイアック・ライヴ』の音だけテープに録音してもらって聴いてたなー。 ソフトも高かったが、その頃にはハードも値段が下がってきていたとはいえ、HI-FI録画再生ヴィデオ・デッキは定価200,000円以上はしていたと思う。今回記憶を頼りに私が買ったヴィデオ・デッキをネットで探してみたら、私が買ったのは、Victor HR555というデッキで定価は218,000円。1985年にグッドデザイン賞を受賞しているので、たぶん1986年頃に購入したのかなぁ。たしかバイト代貯めて買った覚えがある。私が『パラノイアック・ライヴ』のソフトを購入したのは廉価再発になった3,400円(税抜)型番:34HC-345のVHSテープ(右上のジャケ写)。 ラフォーレミュージアム赤坂のステージにはロシア語・キリル文字...