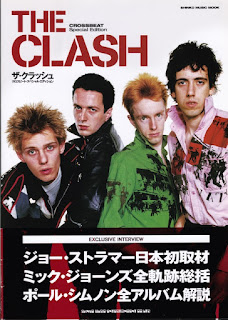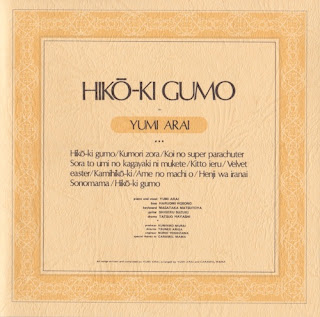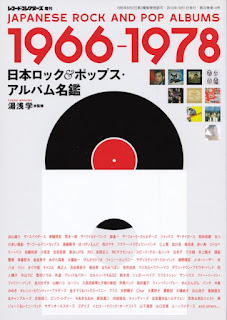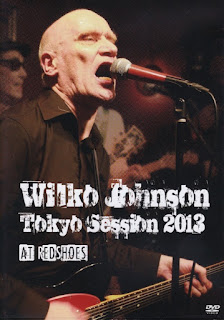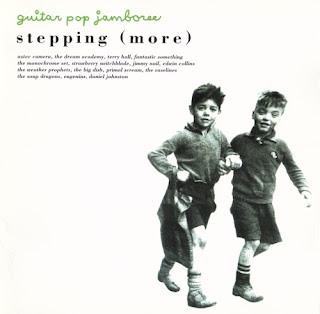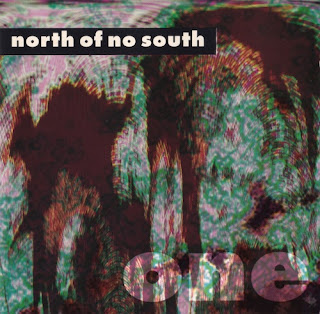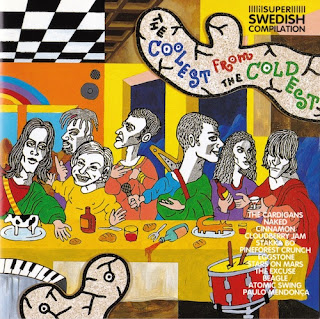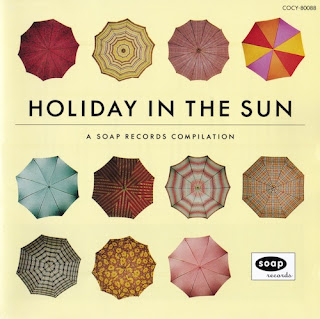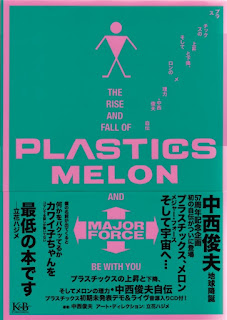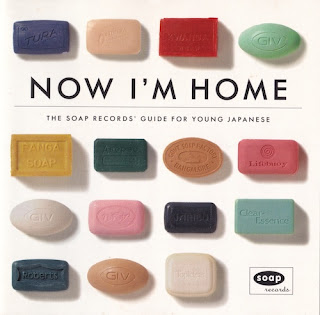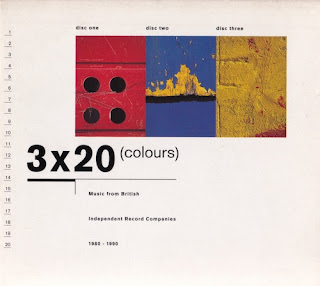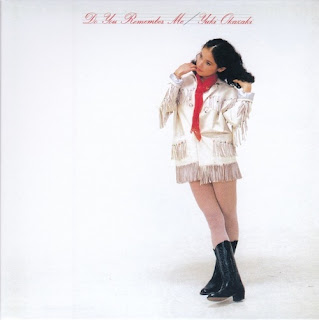MIKE OLDFIELD「MOONLIGHT SHADOW」

1983年5月リリースのアルバム『Crises』より。 NHKのEテレで時々放送されている「ミュージック・ポートレート」(シーズン3が9月で終わった)は、これまでの人生で影響を受けた音楽10曲を2人の出演者が持ち寄って対談するという内容の番組だが、見ていると時々 “これ聴いてみたいな” という曲が紹介される。 この「Moonlight Shadow」は今年の5月に放送された“よしもとばなな×サンディー”の回で、よしもとばななが4曲目に作家デビューのきっかけ、として選んでいた曲。これを見たとき(聴いたとき)、“あーマイク・オールドフィールドってボーカル入りのポップな曲があるんだ”と思った。マイク・オールドフィールドといえば一部が映画『エクソシスト』で使われた『チューブラー・ベルズ』しか持っていなかったので、プログレ系インストの人、というイメージがあった。余談だけどこの『チューブラー・ベルズ』を購入したのも『エクソシスト』を観てすぐじゃなく(公開年に観た)、1990年代に車の中で聴いた小林武史のFMラジオ番組でアナログ1面分(約20分)がかかっていたのを聴いて面白いなと思って購入したものだ。 良い曲だ、とは思ったものの「Moonlight Shadow」はその後、どのアルバムに収録されているのか調べることもせず、CDを購入することもなく忘れていたのだが、先日友人から譲ってもらったCDの中にアルバム『Crises』が含まれていたという非常にうれしい出来事がありこの名曲が聴けることとなった。調べてみればアルバムと同じ時期に、この曲はシングル・リリースされてイギリスではトップテンヒットになっていることから、当時どこかでこの曲を耳にしていたのかもしれないが、その頃の私の興味ではなかったのだろう。 エイトビートをしっかり刻むサイモン・フィリップスのドラムにエコーのかかったマギー・ライリーの澄んだ歌声、歯切れの良いマイク・オールドフィールドのギター、それにフェアライトCMIの響き。幻想的なムードにつつまれた3分半の非の打ち所がない完璧なポップ・ソングとも思える。 だけど歌われている内容は、銃撃により突然亡くなった彼を想い、彼に会いたい、という歌詞で、曲の(一聴して)爽やかな感じと裏腹に悲しく切ないものだ。この歌詞については1980年のジョン・レノン殺害に影響を受け作られたとも言われ...