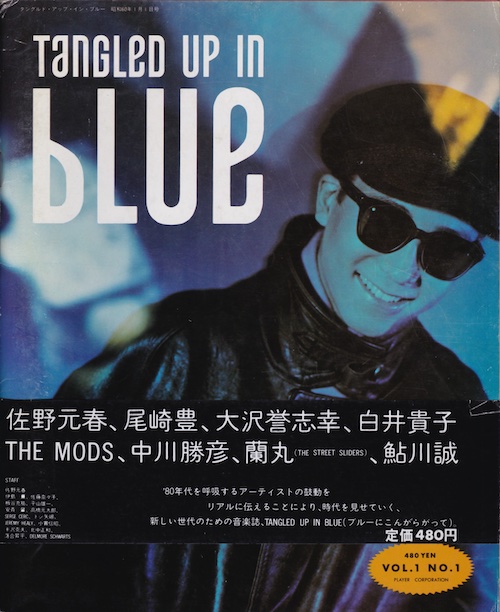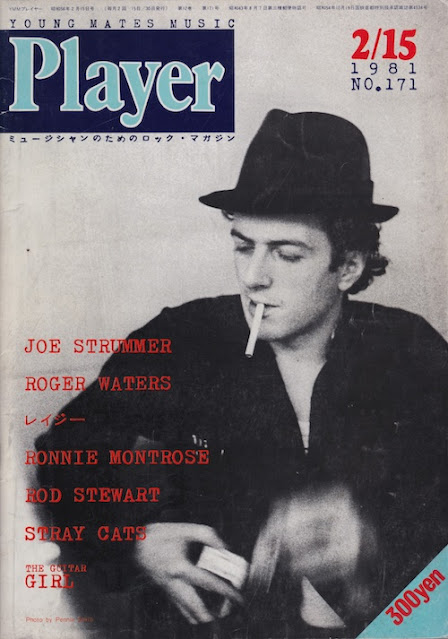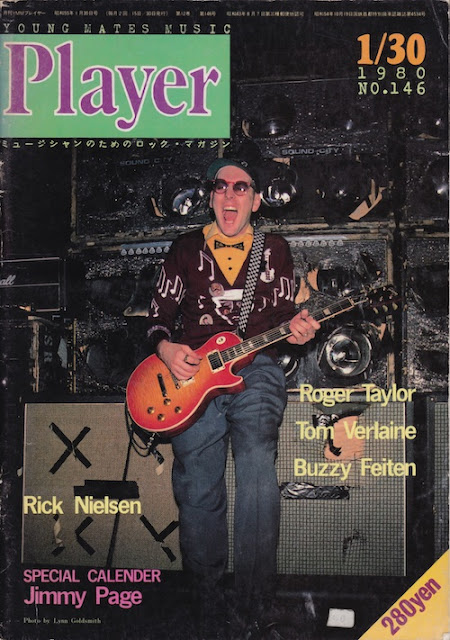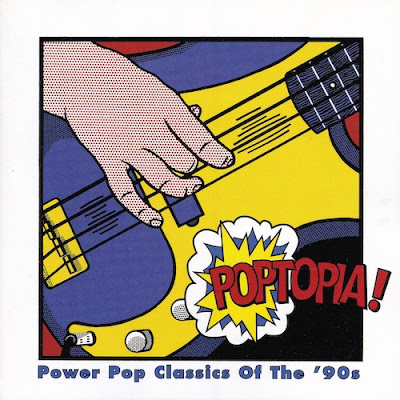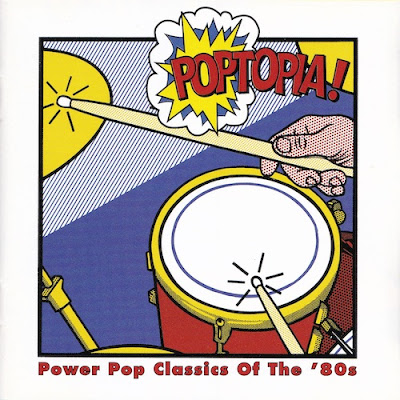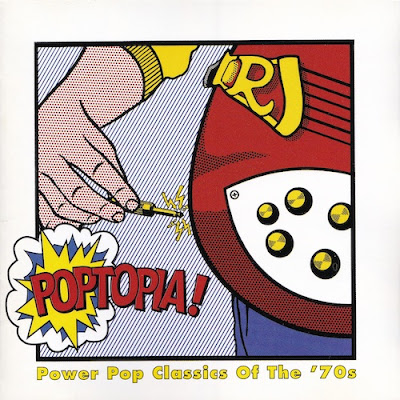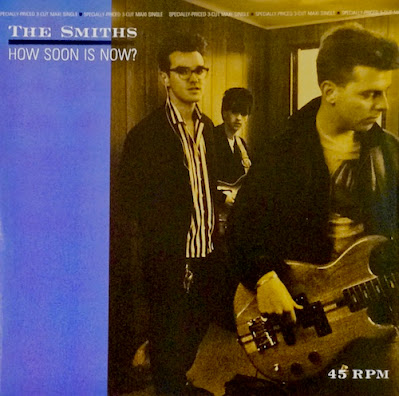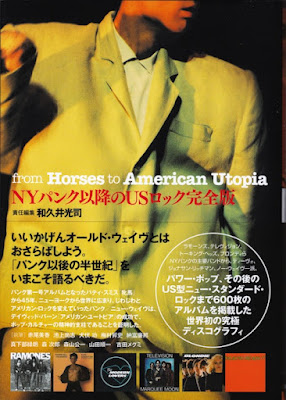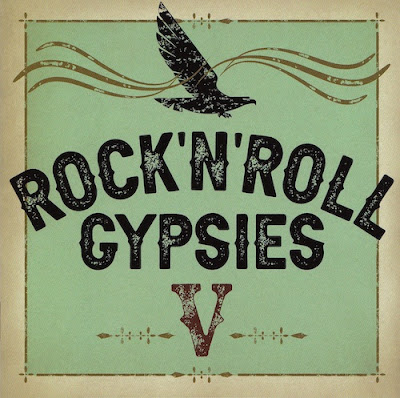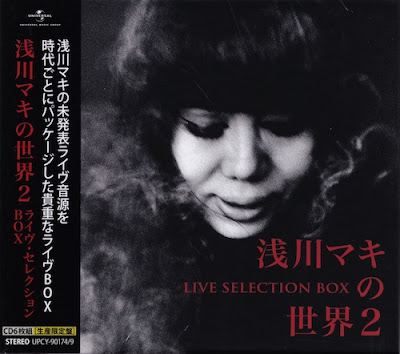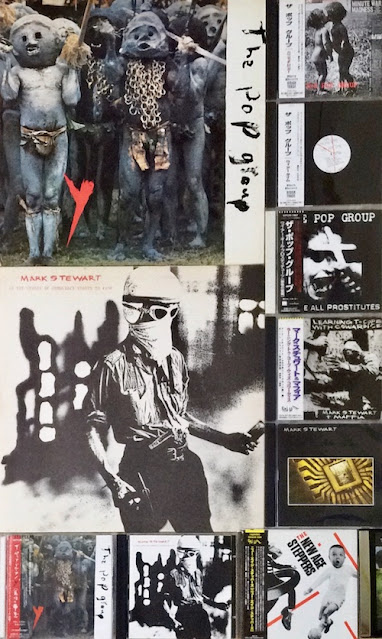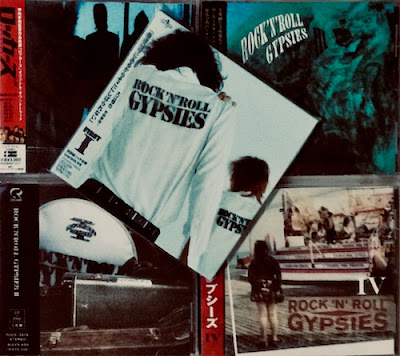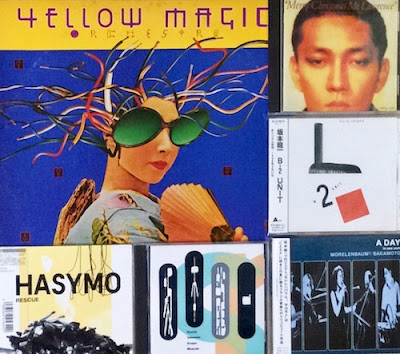ザ・ルースターズ後の大江慎也のベスト盤というと1989年にリリースされた『カレイドスコープ 1986-1989』があるけどこれはリミックスが施され全曲英語詞ヴァージョンという仕様だった。 同じ頃、自分でも選曲してカセット・テープに録音してベスト盤を作ったが、カセットはだいぶ処分したので残ってない。その後(2001年頃だと思う)MDレコーダーを買ったので1988年のCDシングルや1990年にリリースされたアルバム『WILL POWER』(+ONES名義)からも選曲してMDに録音した。その後CD-Rにも録音したなぁ。 1990年に音楽活動を一時停止、その後大江が語ってきたポートレイト・レコード(つまり柏木省三)との確執。自分の意思が反映されていない内容だとポートレイト絡みのリリース作品を否定する大江慎也。だけどあの頃大江の作品を追いかけ、突き抜けた作品となった4枚目のアルバム『PECULIAR』は特に気に入ってたしライヴにも行った。この頃ニューオーダーの『テクニーク』を愛聴してたから大江のダンサブルなデジタル・サウンド(とアコースティックなサウンドの共存)は歓迎だったが、それほど間を置かずにONESを伴ってハードなギターを軸にしたバンド・サウンドに回帰したのは個人的にちょっと残念だったな。まぁこの後来る潮流を見据えた変化だったのかもしれないけど。 以下、私の選んだ、THE VERY BEST OF SHINYA OHE PORTRAIT YEARS 1987-1990。 1. LALALA(作詞:大江慎也 作曲:柏木省三) 2. Just Walkin' That Road(words・Mary / music・Shozo, Tamotsu) 3. She's Got A Way (No No No)(words・Mary / music・Tamotsu, Syozo) 4. Peculiar(作詞:大江慎也 作曲:重藤功) 5. Kaleidoscope(words・Shinya, Mary / music・Shinya) 6. Drooping Affection(words・Yamazen / music・Katsuyuki) 7. Tonight(作詞・作曲:柏木省三) ...