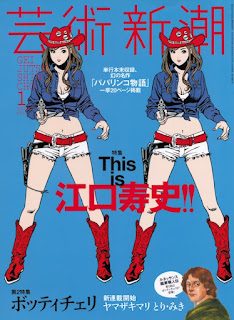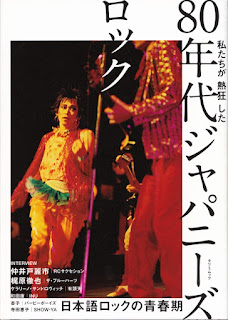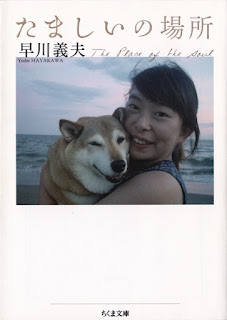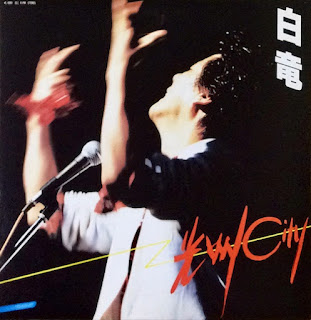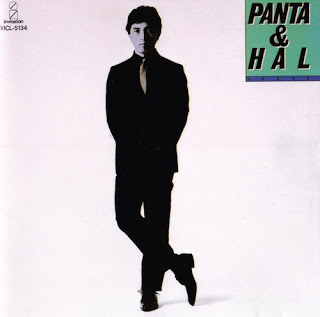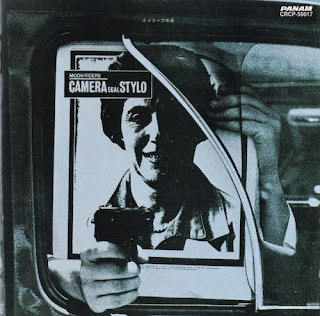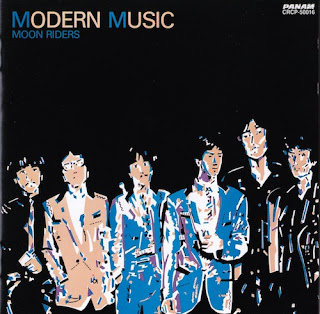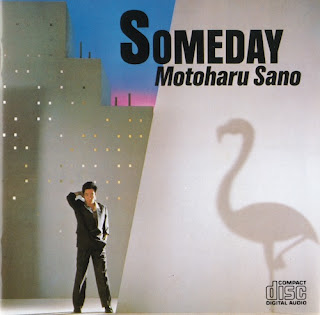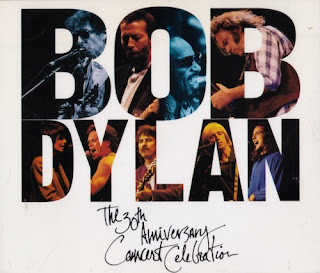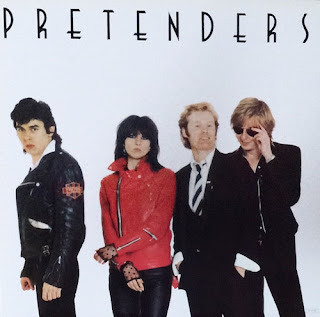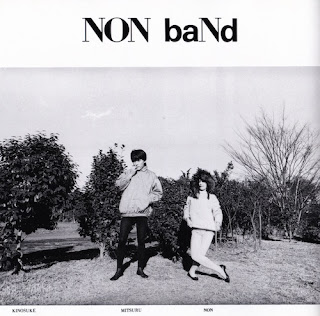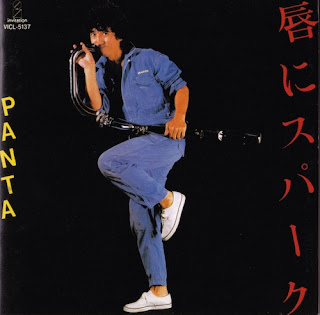1990年、BMGよりリリースのコンピレーション・アルバムより。 1982年のクラッシュ来日公演のテレビ放送やラジオ音源を見聞きして、メンバーが登場する時にかかっているカッコいいオープニングSEは何の曲だろうな、と思った。 後にウェスタンの映画音楽を使用しているというのはどこかで読んだのだろうけど、そういうウェスタンな雰囲気を持った曲だった。クリント・イーストウッドのマカロニ・ウェスタンは好きでテレビで放送される度に見ていた。どうやらそのイーストウッド主演のマカロニ・ウェスタンの曲を使っているらしい…でも、どの映画に使われている、何ていう曲なのか…。やはり有名な『荒野の用心棒』、『夕陽のガンマン』、『続・夕陽のガンマン』のどれかだろう…などとあたりをつけて…。 家に『続・夕陽のガンマン』のテーマのシングル盤があった(父親が買ったんだろうな)。原題は“The Good, The Bad And The Ugly”、エンニオ・モリコーネ楽団の演奏だ。聴いてみると、これは違うな…。そのシングルB面には『夕陽のガンマン』のテーマが収録されていた。原題“For A Few Dollars More”。こちらはギター演奏に編曲されているようだ。聴いてみると、これも違うな。それからまぁ熱心に探してた訳じゃないが、ウェスタン・テーマ・ソング集みたいなレコードを買ったりしてたんだけど探し当てられなかった。 探していた曲のタイトルが「Sixty Seconds To What?」だと知ったのはいつ頃だろう。『リデンプション・ソング(ジョー・ストラマーの生涯)』には記載があるから、この本で知ったのかも…。ジョーが亡くなった後の2007年に出版された本だから、ずいぶん長い時間が経ってるな…。 「Sixty Seconds To What?」は1965年セルジオ・レオーネ監督、クリント・イーストウッド主演のイタリア製西部劇映画『夕陽のガンマン』に使われていた曲で、イーストウッドが活躍している場面じゃなく、イーストウッドが探しているお尋ね者たちがアジトで裏切者を始末するところで使用されていた。60秒(Sixty Seconds)というのは、映画に登場する懐中時計がオルゴールになっていて、蓋を開けてオルゴールの音楽が鳴り、音楽が終わるまでが60秒、蓋を開けてオルゴールを鳴らすということが対決する...